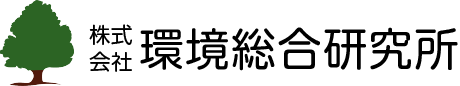TNFDに対応する自然資本データの役割
いま、企業経営における自然資本への対応が急速に求められる時代に突入しています。その背景にあるのが、2023年に正式にフレームワークが公開されたTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の存在です。気候変動に対するTCFDの自然資本版とも言えるTNFDは、企業や金融機関に対して、生物多様性や生態系サービスといった“自然”との関係性を把握し、財務的影響を含めた情報開示を行うことを促すものです。
このTNFDの要請に応えるためには、企業が自社の事業活動やバリューチェーンを通じて、どのような自然資本に依存し、どのような影響を及ぼしているのかを把握・評価する必要があります。しかしこの「自然資本との関係性の可視化」は、従来の財務・非財務データだけでは容易に対応できません。ここで鍵となるのが、環境デューデリジェンス(環境DD)を通じて得られる自然資本データの活用です。
環境DDとは本来、M&Aや事業投資、不動産取引などに際して、対象となる土地や施設に環境リスクが潜在していないかを評価する調査プロセスです。土壌・地下水汚染、大気排出、排水の処理状況、廃棄物の管理状態、生態系への影響などを把握するため、文献調査や現地調査、関係者ヒアリング、サンプリング調査などを組み合わせて行われます。
この環境DDを、TNFDにおける自然資本評価のインフラとして位置づけ直す動きが、いま注目されています。なぜなら、環境DDの現場ではすでに、自然資本に関する極めて重要な情報が収集されているからです。
たとえばある土地の開発を検討する際、環境DDではその土地の過去の利用履歴や周辺環境、自然植生や水循環、生態系保全区域との関係性などを調査します。これらはすべて、TNFDで求められる「立地に関する依存・影響の評価」の出発点そのものです。さらに、排水や大気排出に関する計量証明、工場周辺の自然環境のモニタリングデータ、土地改変履歴の空間情報などは、自然資本とのインターフェースを定量的に評価するための貴重な一次データといえます。
TNFDフレームワークでは、「LEAPアプローチ(Locate, Evaluate, Assess, Prepare)」と呼ばれる4段階の手順が示されています。まず事業活動と自然資本の接点をLocate(特定)し、次に依存と影響の内容をEvaluate(評価)、リスクと機会をAssess(分析)し、最後に情報開示と経営対応をPrepare(準備)するというものです。環境DDは、このうち前半の「Locate」と「Evaluate」を実務的にカバーする極めて有効な手段といえます。
例えば、地下水を多く使用する飲料メーカーであれば、操業拠点ごとの地下水涵養能力と取水実績を環境DDで調査することで、「依存」の構造が明らかになります。また、同時に排水が下流の湿地帯や保全対象河川に与える影響を把握すれば、「影響」の評価も可能です。このように、環境DDの枠組みを通じて、事業と自然資本の関係を体系的に“見える化”することは、TNFD開示の第一歩としてきわめて実効性が高いのです。
さらに、近年の環境DDでは、従来の汚染物質リスクに加えて、生物多様性や生態系への影響を含めた評価が強く意識されるようになっています。具体的には、周辺に希少種の生息地が存在するか、緑地や湿地などの自然環境が分断されていないか、土地改変が地域生態系ネットワークに影響を与える可能性があるかなど、かつては“外部環境”として扱われていた自然要素が、事業リスクの一部として再定義され始めているのです。
この変化は、単なる評価範囲の拡大にとどまりません。企業にとっての自然資本とは、リスク源であると同時に、レピュテーションや地域共生の観点から機会にもなり得る資源です。水源涵養林の保全、在来種と共生する緑地設計、自然再生による生態系サービスの回復──これらは、環境DDの枠内でも十分に検討可能な戦略であり、自然資本の「正味の価値」を高める方向性です。
今後、TNFDに対応する開示を進めるうえで、企業や自治体が陥りやすいのは「抽象的なガイドラインをどう実務に落とし込むか分からない」という課題です。その際、環境DDという既存の調査手法に立脚することで、自然資本評価は“実行可能なもの”として現場に根づいていくのです。環境調査・計量証明を担う専門機関が、自然資本評価の第一線で果たせる役割は今後ますます大きくなっていくでしょう。
まとめ
TNFDが求める自然資本の評価と情報開示は、決してゼロから構築すべきものではありません。その実務的な基盤として、環境デューデリジェンス(環境DD)は極めて有効な手段となります。環境DDを通じて得られる一次データや現場情報は、自然資本への依存と影響を可視化し、リスクと機会の評価を可能にします。これからの環境DDは、単なるリスク評価を超えて、自然資本の価値を理解し、活用し、守るための“戦略的ツール”として位置づけられていくでしょう。