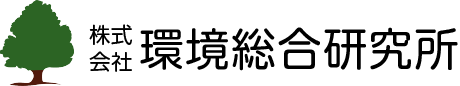統合的アプローチが拓くネイチャーポジティブな未来
気候変動への対応、資源循環の強化、生物多様性の保全。これらは現代社会が直面する喫緊の課題であり、それぞれ「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー」「ネイチャーポジティブ」という概念で体系化されつつある。こうした環境分野の潮流は、もはや個別の対策としてではなく、企業や自治体の戦略的な意思決定と密接に結びつく統合的アプローチとして再定義されつつある。本稿では、それぞれの概念の相互関係と統合の意義、そして実務における接点について解説し、これからの環境調査や環境デューデリジェンスの方向性にも言及する。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを目指す概念であり、企業にとっては製品ライフサイクル全体の排出量把握と削減対策、さらにオフセット措置までを含む包括的な取組が求められる。2050年カーボンニュートラルの目標は世界的に共有されており、日本でも政府によるGX(グリーントランスフォーメーション)戦略が進む中、多くの企業が脱炭素戦略を中核に据えた経営に移行している。
一方、サーキュラーエコノミーは従来の「つくって、使って、捨てる」直線型経済から脱却し、資源を可能な限り循環させることを目指す経済モデルである。再使用(リユース)、再生(リサイクル)、再製造(リマニュファクチャリング)などを通じて、廃棄物の発生を最小限に抑えながら経済活動を継続する。近年では、リサイクル率の向上だけでなく、製品設計段階から「廃棄を生まない」思想を取り入れる「エコデザイン」も重要視されている。
これら二つの概念は、排出削減と資源循環という異なる軸を持ちながらも、実務上ではしばしば重なり合う。たとえば製造業において、材料ロスを抑制し再生資材を活用することは、資源循環に寄与すると同時に製造時のエネルギー投入量を削減し、カーボンフットプリントの低減にも直結する。また、調達段階での資源選定や物流効率化も、両者の目標に資する行動として評価される。
そこに第三の軸として浮上してきたのが、「ネイチャーポジティブ」の考え方である。これは「自然への悪影響を減らす」ことを超えて、「自然を回復・再生させる」ことを目標とする新たな環境ビジョンであり、2022年の生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」によって世界的に位置づけられた。企業や自治体は今後、自らの事業活動が自然資本に与えるインパクトを評価し、その回復や生態系再生にどう貢献するかを問われることになる。
ここで重要なのは、これら三者がそれぞれ独立した施策ではなく、重層的に連携しうる戦略的フレームであるという点である。たとえばある地域における再資源化施設の導入は、廃棄物削減(サーキュラー)と温室効果ガス排出削減(カーボン)を同時に達成しつつ、森林・水系への廃棄物流出リスクを軽減することで生態系保全(ネイチャーポジティブ)にも貢献する可能性がある。
企業にとっては、こうした統合的視点が、今後ますます求められる非財務的情報開示の土台ともなる。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に続き、自然資本に焦点を当てたTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が注目されており、リスクと機会の把握、インパクトの定量化、そして戦略との統合が開示の核心をなす。その前提となるのが、正確かつ実証的な環境調査であり、定量的なモニタリング、GIS(地理情報システム)やリモートセンシング技術を活用した広域評価、そしてステークホルダーとの対話による意味づけの共有である。
また、企業買収や新規事業開発の現場では、環境デューデリジェンス(環境に関するリスクと負債の事前調査)が重要性を増している。特に近年は、単なる土壌汚染やアスベストの有無にとどまらず、生態系への影響や気候レジリエンスの評価も対象となっており、ネイチャーポジティブの観点から「どのように地域と共生できるか」が評価軸となる。
自治体においても、これら三つの概念は個別の施策ではなく、まちづくりや地域経済の構造転換の軸として統合されつつある。カーボンニュートラル宣言を掲げる自治体では、再生可能エネルギー導入や公共施設の省エネ化に加え、地域資源を循環させる仕組みや、生物多様性保全と観光振興を両立する「自然共生サイト」の整備も進んでいる。自治体計画における環境評価指標も、CO₂削減量に加えて、資源循環率や自然資本へのインパクト評価といった新しい視点が導入されつつある。
以上のように、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブは、それぞれ異なる課題へのアプローチでありながら、共通の現場──つまり企業のサプライチェーンや地域の暮らし──においては、複合的に作用し合う関係にある。単一の施策では到達できない環境価値を創出するためには、各概念のつながりを意識した全体設計が欠かせない。
まとめ
気候変動への対応(カーボンニュートラル)、資源循環(サーキュラーエコノミー)、そして生物多様性の回復(ネイチャーポジティブ)は、現代社会の三大環境目標とも言える。本稿で見てきたように、これらは相互に影響し合い、統合的に進めることで真の持続可能性に近づく。企業にとっては環境調査や環境デューデリジェンスがその第一歩となり、自治体にとっては地域資源の再評価と循環構築が鍵を握る。私たちは今、環境の三本柱をつなぐ新しい時代の起点に立っている。