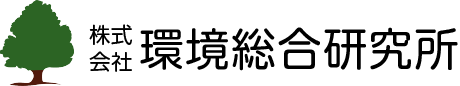環境調査と環境デューデリジェンスの違いとは
私たちが「環境調査」や「環境デューデリジェンス(以下、環境DD)」という言葉を耳にする機会は、企業活動や自治体施策が環境に深く関わる場面で少しずつ増えてきました。しかし、この2つの言葉はいずれも環境にまつわる「調査」を意味し、土壌汚染や地下水汚染、大気・騒音・振動、廃棄物の不適正管理などといったインシデントの確認や防止にかかわる活動です。けれども、両者のスタンスは決定的に異なります。環境調査が「起きてしまった問題」に対処する後追い型の手法であるのに対し、環境DDは「まだ起きていない問題」に対して備える予防型の調査なのです。
環境調査とは、例えば操業中の工場で土壌汚染が疑われた際に、その範囲や濃度、汚染の由来などを明らかにする調査です。これは不動産取引時や操業停止後の土地再利用時に、「想定外の汚染」が発見されたときなどに実施されるケースが典型です。行政指導や訴訟リスクが発生した段階で、その原因究明と責任範囲の確認、さらには修復措置を検討するために、調査が必要となるのです。つまり、リスクが既に顕在化した“結果として”求められる対応なのです。
これに対して、環境DDは主にM&Aや不動産取引、資産評価などの局面で、取引対象の資産や事業が「環境リスクを潜在的に抱えていないかどうか」を事前に調べる手続きです。これは、実際に汚染や法令違反が起きているかどうかを確かめるだけでなく、「将来的に問題が生じる可能性がある要因」がないかをチェックすることに主眼があります。たとえば、過去の使用用途に起因する土壌汚染リスクや、地下タンクの管理状況、排水処理施設の運転記録、PCB等の有害物質の保管履歴といったデータを広範に調査・分析することで、潜在リスクの把握と対応方針の提案を行います。
ここで重要なのは、環境DDは単なる「調査」ではなく、「将来に向けた意思決定の材料」としての役割を担っているという点です。企業にとっては、M&A後に多額の修復費用が発生するような事態を回避するため、あるいは自治体が土地利用計画を策定する際に、公共投資が無駄にならないよう、あらかじめ環境的なリスクを精緻に見積もることが求められています。これは単に事前のリスクを知るという行為にとどまらず、「環境インシデントの予防」に寄与するという点で、社会的にも意義深い行動といえるでしょう。
また、両者の調査アプローチには、用いる手法や求められる視点にも違いがあります。環境調査では、特定の汚染物質の有無や法令違反の確認など、「現場の実態を正確に測定すること」に主眼が置かれます。一方、環境DDでは、汚染の有無に加えて、「過去の使用履歴」や「関係書類の整備状況」、「設備や建築構造の劣化リスク」など、将来的なトラブルの兆候を洗い出すための情報収集と、リスク分析・評価のプロセスが重視されます。
こうした調査の実施主体も、目的によって異なる場合があります。環境調査は、行政の指導の下で実施されるケースや、第三者機関の検証を受ける必要があるケースも少なくありません。これに対して環境DDは、買収や取引における「自己責任原則」に基づく民間のリスク評価であり、投資判断や契約条件の調整に活かされるため、より戦略的な判断材料としての性格を帯びています。
さらに、ここであえて強調したいのは、「環境DDの実施によって、環境インシデントが未然に防がれ、結果として環境調査を“行わずに済む”ケースがある」という点です。環境DDは、環境法令の遵守状況や設備管理体制を第三者の視点で点検するプロセスでもあるため、たとえば排水処理施設の更新計画の遅延や、廃棄物保管エリアの不備といった、日常の運用に紛れ込みやすいリスクも早期に発見できます。こうした予防的措置は、企業のレピュテーションを守り、ESGの観点からも極めて重要な投資と評価されるべきです。
環境DDは近年、金融機関によるESG投融資や自治体の都市開発においても注目を集めています。自然共生サイトやネイチャーポジティブ経営への関心が高まる中で、企業や行政は「環境に配慮している」というだけでなく、「環境リスクをマネジメントできる体制を持っているか」が問われるようになりました。従来の「環境調査」はこの問いに対して後追い的な回答しか提供できませんが、「環境DD」はより積極的に、経営戦略の一部として環境配慮を組み込むことが可能になります。
もちろん、すべての場面で環境DDが求められるわけではありません。小規模な土地取引や、既に長年使用されてきた施設においては、法的要請に基づく環境調査の方が適切なケースもあります。しかし、複雑化するサプライチェーンや不動産の高付加価値化が進むなかで、「事前にどこまでリスクを読み取れるか」は、経済合理性の観点からも企業や自治体にとって重要な能力となりつつあります。
まとめ
環境調査と環境デューデリジェンスは、いずれも環境に関するリスクを把握するための手段ですが、その目的と活用されるタイミングには大きな違いがあります。環境調査が既に発生したインシデントへの対応としての「後追い型」であるのに対し、環境DDはリスクが顕在化する前にその兆候を探り、未然に対処する「予防型」の調査です。企業経営や自治体計画がESGやネイチャーポジティブといった持続可能性の要請に応えるためには、この「予防的視点」に立った環境DDの重要性がますます高まっています。今後、社会全体で「環境リスクをどう予測し、どうマネジメントするか」が問われるなかで、環境DDは単なる調査を超えた戦略的アプローチとして、その存在感を強めていくでしょう。