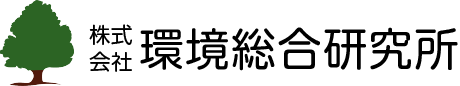環境デューデリジェンスと計量証明事業
環境デューデリジェンス(以下、環境DD)は、企業活動や資産取引、サプライチェーンの管理などにおいて、環境リスクを事前に把握・評価するための重要なプロセスとして広く認知されるようになってきました。特にM&Aの局面では、買収対象の土地や事業所に土壌・地下水汚染、廃棄物の不適正保管、法令違反といった環境的な瑕疵がないかを調べるために実施されるケースが多く見られます。
その環境DDの実行プロセスにおいて、決して欠かすことのできないステップが「環境調査・計量証明」です。これは単に付随的な分析作業ではなく、環境DDの信頼性そのものを支える中核的な機能です。環境リスクの有無を判断するうえで、環境の一次データを正確に取得し、科学的に分析し、定量的に評価する作業は、調査全体の論拠を築く根幹にあたります。言い換えれば、調査結果の根拠となるデータの精度と真正性が確保されてはじめて、環境DDは企業や行政が意思決定を行うための材料たり得るのです。
計量証明事業とは、環境基本法や各種公害防止法に基づき、大気・水質・土壌・騒音・振動・悪臭などを対象に、認可を受けた専門事業者が測定・分析を行い、その結果を公的に証明する制度です。この事業には、法令遵守・品質保証・測定技術といった厳格な基準が課されており、その精度と信頼性は極めて高いものとされています。環境DDにおいて必要なボーリング調査、土壌採取、地下水分析、ガス調査、騒音測定などは、すべてこの制度下のスキームで行われます。
にもかかわらず、これまで環境DDの現場では、ファイナンシャルアドバイザーや戦略コンサルタントといった非専門の中間支援者が、環境面の評価の一部として「調査会社にデータ取得だけを外注する」という構図が多く見られました。この場合、環境調査・計量証明の専門知見を十分に理解しないまま報告書が作成されることもあり、調査結果の意味づけや、リスクの実態に対する判断が表層的になるリスクをはらんでいました。
実際には、土壌中の汚染濃度がどの程度であるかだけでなく、それが自然由来か人的由来か、将来的な拡散可能性や除去・封じ込めの技術的妥当性、そして修復にかかる費用や期間といった実務的な知見も踏まえなければ、実効性のあるリスク評価はできません。これらの判断には、データそのものの意味や、現場環境の制約、制度的対応の可能性などを統合的に理解している専門家の視点が不可欠です。
だからこそ、今後の環境DDにおいては、環境調査・計量証明の専門家こそが「一気通貫」でリスク項目の設定から調査、評価・報告書作成までを担うべきだという見方が強まっています。環境データは単なる“数字”ではなく、自然環境の変化や事業活動の影響を読み取るための“言語”であり、それを読み解くには、日々現場に向き合い、測定・分析を実践している専門事業者の知見が最も信頼に足るのです。
また、近年の環境DDでは、TNFD(自然関連財務情報開示)やEUの企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)への対応を念頭に置いた「戦略的調査」としての性格も強まっています。企業のネイチャーポジティブ経営や、ESGスコアの向上、自社の自然資本依存の定量化などを目的とした「セルフDD」の場面においても、客観的かつ再現可能な環境データの存在が不可欠です。
こうした文脈の変化に対応するには、調査技術だけでなく、政策動向や開示基準、修復技術、予算設計、関係者との調整までを総合的に理解し、判断できる人材の関与が必要になります。環境調査・計量証明のプロフェッショナルがその役割を担い、リスク項目を設定し、DDの設計から調査、評価、助言までを一体的に実施することで、より実践的で説得力のある環境DDが可能となるのです。
企業や自治体の環境DDへのニーズは、単なる「リスク把握」から、「価値創造」や「持続可能性の担保」へと進化しています。その中で、信頼できる一次データを収集・分析・解釈できる環境調査・計量証明の専門家の役割は、ますます不可欠なものとなっています。
まとめ
環境デューデリジェンスの信頼性は、現場から得られる環境一次データの精度と、それを正確に読み解く専門知見に支えられています。従来は環境調査部分のみを外注する形でDDが進められることも多くありましたが、これからは環境調査・計量証明の専門家がプロセス全体を主導し、一気通貫で調査・評価を担うことが求められます。データを取得するだけでなく、それが何を意味するのか、どう活用すべきかを深く理解してこそ、環境リスク評価は実効性を持ち、企業・自治体の持続可能な意思決定を支える力となるのです。