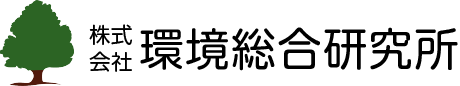廃棄物処理法から考えるサーキュラーエコノミー
近年、「サーキュラーエコノミー(循環経済)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。これは、資源の使用をできるだけ効率化し、廃棄物の発生を最小限に抑えながら、限りある資源を循環させて使い続けるという考え方です。気候変動や資源枯渇への対応が求められる中、この考え方は世界中で注目されています。そして、日本においてこの循環的な社会の実現を支えている法制度のひとつが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、いわゆる廃棄物処理法です。本稿では、廃棄物処理法の成り立ちとその進化を踏まえ、サーキュラーエコノミーの視点からその意義を見直してみたいと思います。
廃棄物処理法が誕生したのは1970年。当時の日本は高度経済成長の真っ只中にあり、工業化に伴って工場排水や廃棄物の問題が深刻化していました。従来の「清掃法」では市街地の衛生維持が中心であり、産業によって生み出される有害物質や大量の廃棄物に対処しきれず、水俣病やイタイイタイ病といった重大な公害が社会問題となりました。こうした背景のもと、生活環境の保全や公衆衛生の向上を目的として新たに整備されたのが廃棄物処理法です。この法律では、廃棄物の種類や処理方法に応じた責任分担が制度化され、事業者の責任が明確にされました。産業廃棄物の定義や処理フロー、自治体の許認可制度など、現代に続く制度的枠組みの基礎が築かれたのです。
しかし、廃棄物処理法は、制定当初は「捨てること」を前提とした法制度でした。廃棄物をいかに適切に処理し、環境や衛生に悪影響を与えないようにするかが中心的なテーマであり、いわば「後始末」の視点が強くありました。ところが1990年代に入り、世界的に環境問題への関心が高まる中で、この法律も転換期を迎えます。1991年の改正では、廃棄物の発生をそもそも抑制すること、そして再資源化を促すことが法律の目的に加わりました。いわゆる「リデュース(発生抑制)」と「リサイクル(再生)」の考え方が、法的にも明確に位置付けられるようになったのです。
この改正以降、廃棄物処理法は「ごみ処理法」から「資源循環法」へと徐々にその性格を変えていきます。家電リサイクル法、食品リサイクル法、容器包装リサイクル法など、廃棄物処理法を補完する個別リサイクル法が次々と制定され、特定の分野における再資源化の仕組みが整えられていきました。さらに、近年では2022年の「プラスチック資源循環促進法」、2024年の「資源循環促進高度化法」など、設計段階からの資源循環を促す新法も導入され、サーキュラーエコノミーの理念に沿った法整備が進められています。つまり、廃棄物処理法は単なる「廃棄物をどう処理するか」という観点にとどまらず、「廃棄物を資源としてどう活かすか」という新しい発想のもとに、制度的に進化してきたのです。
とはいえ、現場の運用面ではまだ課題も多く残されています。たとえば、リユース(再使用)は法的には廃棄物に該当しないため、制度の対象外となっています。結果として、リユースの推進には民間の自主的努力や市場原理に頼る部分が大きく、制度的な後押しは限定的です。また、産業界においても、リサイクルコストや収益性の確保といった現実的な制約から、循環的な仕組みの導入が進みにくいという声も聞かれます。さらに、制度が整備されても、それが実効性を伴って社会全体に浸透していくには、行政、事業者、消費者がそれぞれの役割を果たす必要があります。制度だけでは循環は実現できないのです。
サーキュラーエコノミーの実現には、製品の設計段階から回収・再利用までの一連の流れを最適化し、価値を循環させるという大きな視野が必要です。廃棄物処理法は、その中でもとりわけ「最後の出口」を管理する役割を担っており、この出口が適切に機能することで、循環の輪は閉じられます。そして今後は、「出口」の管理にとどまらず、原材料の選定や製品設計の段階から循環を意識した支援が求められていくことでしょう。
環境総合研究所では、こうした制度の変化や実務運用に精通した専門機関として、廃棄物処理に関する調査・制度設計・実務支援を通じて、企業や自治体とともに持続可能な社会づくりに取り組んでいます。廃棄をめぐる制度は、単に「いらないものをどう処理するか」ではなく、「どのように資源として循環させるか」という未来志向の問いへと変わりつつあります。循環する経済を実現するための道筋を、法制度と現場の知見をつなぎながら、私たちは共に探っていきたいと考えています。