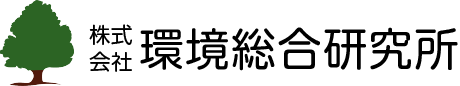廃棄物処理施設の設置と生活環境影響調査
廃棄物処理・リサイクル施設は、一般に騒音や振動、臭気、景観といった点で一定の環境負荷を伴う施設と考えられており、施設の種類や規模によっては、その設置にあたり環境アセスメントの実施が法令や条例によって義務付けられています。とりわけ廃棄物処理法に基づく「生活環境影響調査」は、設置予定地の周辺に暮らす住民の生活環境に与える影響を事前に把握し、適切な措置を講じるための重要な手続きです。現代では当然とされるこの調査義務ですが、その法的制度としての整備が本格化したのは、平成13年(2001年)の法改正が契機となりました。
それ以前、たとえば木くずやがれき類を破砕処理する施設などは、正式な許可制度が存在しないか、あるいは「みなし許可」として届出のみで稼働を続けることができました。1990年代まではこうした簡便な制度でも一定の運用が可能とされてきましたが、実際には地域住民とのトラブルや生活環境の悪化に起因する紛争が増加し、制度の見直しが求められるようになります。これを受けて、2001年の廃棄物処理法施行規則等の改正によって、これらの処理施設についても正式な設置許可と生活環境影響調査の実施が義務付けられることとなりました。
この法改正の意義は、単に手続きを厳格化するというだけでなく、廃棄物処理・リサイクル施設の設置を地域共生型のプロセスへと転換するという意味を持ちます。生活環境影響調査は、施設の稼働によって周辺にどのような影響が出るかを予測し、必要に応じて緩和策を講じることを目的としています。加えて、申請段階での住民説明会や関係市町村の意見聴取、場合によっては縦覧手続きや都市計画審議会での議決といった、住民参加型の仕組みも取り入れられました。これにより、地域の不安や反対を事後的に処理するのではなく、計画段階から合意形成を進めることが法的に位置づけられたのです。
生活環境影響調査の対象となる施設は、焼却施設や最終処分場のような大規模施設に限らず、中規模以下の破砕・選別施設、圧縮梱包施設、堆肥化施設などにも広がっており、近年では個別リサイクル法との関連からより複雑な施設設計や運用が求められるようになっています。とりわけ、木くず・がれき類の破砕施設は比較的小規模であるにもかかわらず、ダンプ車の出入りや騒音・粉じんなど、地域の生活環境に及ぼす影響が看過できないとして、生活環境影響調査の対象とされることが多くなりました。これらは従来、「軽微な施設」として扱われがちでしたが、地域環境との調和を図る観点から、法的な担保のもとで影響評価を行うことが当然視されるようになったのです。
このような制度改正を受け、既存のみなし許可施設についても、増設や用途変更といった場合には新たに生活環境影響調査が求められることとなり、設置者には法的・技術的な対応力が求められるようになりました。また、設置許可の審査においては、環境省が示す「生活環境影響調査指針」に沿った調査計画や予測評価が必要となるほか、周辺地域における既存施設との重複影響など、複合的な検討も求められます。
私たち環境総合研究所では、こうした制度の背景と趣旨を正しく踏まえた調査設計や、住民対応を含む実務支援を多数行ってきました。施設設置者にとっては手続きの煩雑さが負担に感じられる場面もありますが、これらの手続きこそが地域社会との信頼関係を築き、持続可能な資源循環型社会を支えるインフラとなり得るのです。生活環境影響調査は単なる義務ではなく、施設と地域とをつなぐ「対話のプロセス」として機能するものであり、そこにこそ今後の廃棄物処理行政の進化の鍵があるといえるでしょう。
平成13年の制度改正は、そうした未来志向の制度設計へと転換する第一歩となりました。廃棄物やリサイクルをめぐる課題は今後も多様化・複雑化することが見込まれますが、私たちは調査・制度設計・実務支援を通じて、法制度と現場実務を架橋し、循環型社会の推進に貢献してまいります。