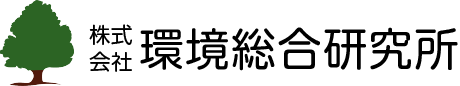企業が担うサステナビリティの両輪
持続可能な社会の実現に向け、企業が果たすべき責任はますます多様化・高度化している。気候変動や生物多様性の喪失といった「環境リスク」に加え、強制労働や差別、地域住民との対立といった「人権リスク」もまた、企業活動の根幹を揺るがす要因として注目されるようになっている。こうした中、企業がリスクの事前把握と対処を目的として実施する「デューデリジェンス(DD)」の対象も、財務情報から非財務領域へと大きく広がってきた。
とりわけ国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)を起点とした「人権デューデリジェンス(人権DD)」と、土壌・水質・廃棄物・大気汚染などに焦点を当てる「環境デューデリジェンス(環境DD)」は、企業のサステナビリティ対応を支える“両輪”とも言える存在である。
この二つのDDは、それぞれ独立した領域で発展してきたが、いまや互いに密接に関係し合い、統合的なリスクマネジメントと価値創造の視点から再構築されつつある。
環境DDは、主に土地・施設の購入や事業買収(M&A)、不動産開発、工場・物流施設の稼働前などに実施され、対象地における土壌汚染、地下水汚染、廃棄物の不適正処理、アスベスト残存などの環境リスクを調査・分析するものである。
一方、人権DDは、サプライチェーンにおける強制労働・児童労働の有無、労働条件、地域住民や先住民族との権利関係などを広範に把握し、企業活動による人権侵害の未然防止と、負の影響への対応策を講じるための枠組みである。
このように対象領域は異なるものの、実務上はしばしば交差する。たとえばある鉱山開発プロジェクトにおいて、環境DDにより現地の水資源への重大な影響が想定される場合、それは地域住民の生活用水や農業、文化的慣習への侵害を通じて人権問題にも波及しうる。また、廃棄物処理や化学物質管理が不十分な施設では、周辺地域の大気汚染や悪臭問題が、健康被害や住民トラブルを引き起こし、企業の社会的信頼を大きく損なう可能性もある。
つまり、環境リスクはしばしば人権リスクと連動しており、どちらか一方の視点では真のリスクの全容を見誤る可能性があるのだ。
このため、近年では「統合デューデリジェンス」として、環境・社会両面を俯瞰しながら、包括的な調査を行う手法が注目されている。具体的には、環境調査における現地ヒアリング時に、住民の声や労働者の作業環境に関する情報を同時に収集したり、サプライチェーン監査において現場の環境管理状況も評価項目に含めたりするなど、領域横断的なアプローチが進んでいる。
こうした動向を受け、欧州連合では「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」が進められており、企業に対して人権・環境双方に関するリスクの特定・予防・是正・情報開示を法的義務として課す方向にある。日本企業においても、グローバル展開や国際調達の拡大に伴い、人権DDと環境DDを“二本立て”ではなく、“一体的”に捉えることが急務となりつつある。
また、環境・人権DDの実施は、単なるリスク回避にとどまらず、企業の長期的価値創出にもつながる。
たとえば、ある製造業では、仕入先の排水管理や廃棄物処理の実態を調査した結果、現地住民の苦情や労働者の健康被害リスクが高まっていることを把握し、改善支援を通じてパートナー関係を再構築。結果的にブランド価値の向上とサプライチェーンの安定化に成功した。
このように、DDは「問題を見つけて切り捨てる」手段ではなく、「課題を共有し、改善に取り組む」対話型のプロセスとして位置づけることが望ましい。
さらに、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)やGRIスタンダードといった国際的な開示フレームワークにおいても、「自然資本と人権」のつながりを重視する項目が増えている。
たとえば、土地利用の変化が地域コミュニティに与える影響や、生態系サービスへの依存度と人間の健康との関係などが、定性的・定量的に開示されるべき内容として整理されており、企業の非財務情報開示においても両者の統合的評価が不可欠になっている。
まとめ
人権デューデリジェンスと環境デューデリジェンスは、企業の持続可能性を支える不可欠な“両輪”である。
それぞれ異なる起点から発展してきたが、現実の事業現場では密接に関係し合い、互いのリスクを深め合う構造を持つ。
だからこそ、両者を分断せず、統合的な視点で調査・対話・改善を進めることが、企業価値の向上と社会的信頼の獲得に直結する。
今、企業に求められているのは、目の前の法令遵守にとどまらず、“人と自然”の未来に責任を持つ戦略的なデューデリジェンスの姿勢である。