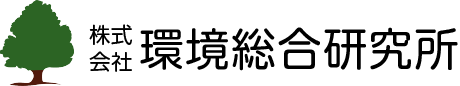ネイチャーポジティブのススメ~ヒトの営みが育む自然環境~
2025年4月、「地域生物多様性増進法」が施行され、国土の30%を「自然共生サイト」として登録する取組が始まりました。この制度は、2030年までに自然の損失を食い止め、回復基調へと転じる「ネイチャーポジティブ」の実現を目指すものです。自然共生サイトの根幹となる考え方は、決して遠い山奥だけでなく、私たちの暮らしのすぐそばにある“身近な自然”にも関係しています。そこで今回から数回にわたり、身近な自然環境とそこに息づく生き物たちの姿を紹介していきます。第1回は「樹林の活用」です。
日本は国土の約7割が森林で覆われているといわれています。その理由は東西に細長く、急峻な地形が山岳地域の開発行為を阻んでいることや、多くの地域が暖温帯に位置し降水量が多いことから、森林を伐採しても時間の経過とともにやがて森林に戻るためと考えられています。たとえ影響の程度が甚大な火山活動による被害であったとしても、富士山の青木ヶ原樹海のように400年程の時が経過すると森林が再生されるのです。
田畑や河川敷でもヒトによる管理が行われずに放置するとクズやセイタカアワダチソウなどの雑草たちに占領され、そのまま放置が続くとやがてススキやアカメガシワなどの先駆樹種の侵入から始まり、カシなどの照葉樹を中心とした樹林へと遷移していきます。
森林の遷移はヒトの寿命と比較するととても長い時間を要することからその移り変わりを見届けることはできませんが、社寺林など古くから保全されている樹林ではシラカシやツバキ、ヤブニッケイなど常緑樹が主体となる照葉樹が茂ったいわゆる「鎮守の森」が残存しており、本来の気候区分に適応した樹林を窺い知ることができます。
ヒトの暮らしの傍らに以前から存在していたクヌギやコナラの雑木林も当時の生活に欠くことができない資源の供給減でした。そのような身近な樹林を「奥山」の対義語として「里山」と呼びます。里山の樹林を構成する樹木は、コナラ、クヌギ、イヌシデ、アオハダ、リョウブなどの落葉広葉樹であり、アカマツやスギなども混植されています。広義的には水田や萱場などもその範疇として考えられています。
これらの樹林は農用薪炭の目的で人工的に維持管理されてきた森であり、田畑への養分補給のために必要となる腐葉土や煮炊きなどに必要となる薪を得る場所でした。筆者が子供の頃には何処でもみることができた雑木林ですが、これらの樹林もヒトが生活するために必要となる燃料を得るために潜在的な植生を開墾して二次的に作られた樹林であることから「二次林」と呼ばれています。

スギやヒノキなどの住宅建築材として有用な木材を生産することが目的の「人工林」でも同様に潜在的な植生を人為的に除去し、目的とする樹種を育林する必要がありそのためには、必要としない樹種の生育を抑制するための作業として「下刈り」が必要となります。「下刈り」作業は植物の生育が旺盛な時期に毎年実施します。他にも床柱などに利用することが出来る節のない良材を得るための「枝打ち」や「間伐」作業など多くの労力が必要となります。手入れの成果により見事成長した樹木が伐採されるのは、植林後50年以上の歳月が経過した後のことなので、これらの育林作業はまさに子孫のための仕事と言えるでしょう。
育林技術もさることながら、材料となる木材をどのように利用すればよいのかを見極めて有効に活用することができる技術者の存在も重要です。材料となる柱が森でどのように生えていたのかを見抜き、将来生じる可能性のある材の反りや捻れ具合の程度を予見して木組みの方法や利用場所を決定します。
お寺の屋根のように建物より大きく張り出した大きな屋根を支える梁などには、成長過程で何度も雪に押し倒され根本が湾曲した「根曲材」を上向きに利用するなどの技術を持った職人さんの存在も日本の林業を支えています。
現在流通している輸入材の多くは、建築現場に届く時点では製材され組み立てる状態で現場に届くので、材の特性を理解する必要も少なくなり製材技術を持った職人さんも少なくなっています。
前述のように植物が繁茂し易い環境である日本の林業は、北米などと比較して維持管理のために生産コストが大きくなってしまうで、木材生産以外の付加価値として地球温暖化防止や水源涵養などの公益的機能を評価する必要が求められます。森林を適切に管理することにより享受することができる機能に相応の代償を支払うという考え方です。
森林の効果としては、気温平準化という概念で都市のヒ-トアイランド化を防止する機能や水源涵養機能として河川水量の平準化や地下水の保全機能、生物多様性の保全などを適切に評価することが大切でしょう。
「地域生物多様性増進法」では「自然共生サイト」の登録審査に際し、その場所が有する価値を絶滅危惧種の存在が確認される場所や移動経路の役割を果たしている場所など9つのカテゴリーに分類して評価します。私たちの行う自然環境調査によりその価値を判断するための環境情報を提供します。その結果は対象地の価値を高めることに役立ちます。
先達たちが暮らしのために必要な資材を得るため樹林管理や畑地の耕作を連綿と繰り返してきました。その人為が及ぶ「半自然的環境」が今日では里山などと呼ばれています。その空間はヒトの利用する環境に適応することができた生物種を中心とする生き物たちで構築された生態系が残存する場所でもあるのです。
Byミズスマシ