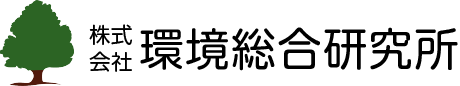ネイチャーポジティブ≠天然記念物の保護
ネイチャーポジティブという言葉を耳にする機会が増えてきた。これは、2022年の「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択以降、国際的に共有されるようになった考え方で、「自然をこれ以上損なわない」だけでなく、「自然を回復・再生させる」ことを目指す新たな方向性として注目を集めている。特に、企業や自治体といった経済・社会の担い手に対しても、ネイチャーポジティブへの貢献が求められる時代となっている。
しかしながら、この概念に対して「天然記念物を守るような専門家の仕事」「保全地域に関わる一部の団体の領域」という誤解が根強いのも事実である。実際には、ネイチャーポジティブは、何も絶滅危惧種の保護活動や希少生態系の保全だけを意味するものではない。むしろ重要なのは、“自分たちの足元にある自然”に目を向け、それをどう活かし、どう再生していくかという姿勢そのものである。
たとえば、ある製造業の企業が保有している敷地内の緑地帯や未活用の社有林。これらは普段、法令対応のための緩衝緑地や単なる「遊休資産」と見なされているかもしれない。しかし実際には、そこに生育する在来植物や飛来する昆虫・鳥類が、小規模ながらも地域の生態系の一部を成している可能性がある。ましてや、都市部において緑が失われつつある今日、そうした“身近な自然”の存在価値はますます高まっている。
国が推進する「自然共生サイト」の考え方も、この流れを後押ししている。「自然共生サイト」とは、保護地域ではない民間・公的な土地の中で、生物多様性保全に実質的に貢献していると認められる区域を指し、条件を満たせば国際目標「30by30」の達成にもカウントされる。このサイトに求められる基準は、単なる美観のための植栽ではなく、外来種ではない在来種の保全、自然再生に資する管理手法、生物多様性を支える生息環境の維持といった点にある。言い換えれば、天然記念物が生息しているかどうかは必須条件ではなく、もっと日常的な自然資産でも、その管理と活用次第で十分にネイチャーポジティブに資することができるということだ。
事実、社有地における緑地帯の整備を通じて、生物多様性保全と企業価値向上の両立を目指す動きも増えてきている。ある企業では、定期的な草刈りや樹木管理を行う代わりに、部分的な自然更新区域を設定し、在来植物群落の再生を図ることで、多様な生物の生息空間を創出している。このような取組みは、直接的な経済的リターンを生むものではないかもしれないが、従業員の自然体験や地域との協働、企業のESG評価といった点で持続可能な企業経営の基盤にもなりうる。
自治体においても、公園の草地やため池、学校裏の林といった何気ない場所における保全活動が、ネイチャーポジティブの要素を満たすことがある。重要なのは、そこに「生物多様性を高める視点」があるかどうかである。たとえば、ため池の管理において農薬の使用を控え、在来種の植生を守ること、あるいは雑木林の間伐管理を通じて多層的な森林構造を維持することも、立派な貢献である。
このような視点は、環境調査や環境デューデリジェンスにおいても変化を生みつつある。従来、環境調査は「問題があるか否か」「法的リスクがあるか否か」に重きを置いてきたが、今後は「自然資本としての価値があるか否か」「積極的に保全・再生すべき対象か否か」という問いへの対応が求められる。社有林や未利用地に対して、ネイチャーポジティブの観点から保全計画を組み込むことで、単なる“リスク要因”だった土地が、“戦略資産”へと変わる可能性がある。特にTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)では、企業が保有する自然資本とその影響・依存関係を開示することが推奨されており、こうした視点は今後、ESG経営の要所になると考えられる。
実務上の工夫としては、まず既存の緑地を定量的に把握し、どのような植生・動物が存在するのかを調査することが第一歩となる。そのうえで、維持管理の方法を見直し、単なる刈払いや除草から「生物の居場所を維持する管理」へとシフトする。また、従業員や地域住民と連携し、自然観察会や市民モニタリングといった活動を通じて、現場の価値を見える化していくことも有効である。
ネイチャーポジティブは、決して遠い存在ではない。私たちの足元にある自然が、適切に評価され、丁寧に手をかけられることで、次世代につながる自然再生の拠点となる。それは、天然記念物のような特別な存在を守ることと同じくらい、いや、場合によってはそれ以上に意味のある行為であるかもしれない。
まとめ
ネイチャーポジティブとは、希少な自然を守るだけでなく、身近な自然と共に歩むことを意味している。敷地の緑地帯や社有林、学校の裏山やため池など、一見ありふれた空間の中にも、生物多様性を育み、回復する可能性は秘められている。大切なのは、それらの価値に気づき、適切に管理・活用していく姿勢である。天然記念物の保護だけがネイチャーポジティブではない。誰もが関われる“足元の自然”こそ、私たちが共生を実践する最前線なのだ。