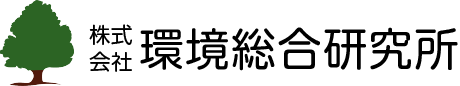「環境DD」最前線
「デューデリジェンス(Due Diligence)」という言葉は、かつて限られた専門家だけが使う法務・財務分野の用語にすぎませんでした。企業の買収・合併、いわゆるM&Aの現場において、投資対象に法的、財務的な問題がないかを事前に確認するプロセスとして確立されたこの概念は、1990年代以降、日本でも徐々に浸透し始めました。そして、その派生形として登場したのが「環境デューデリジェンス(環境DD)」です。
環境DDも当初は、M&Aの文脈で必要とされる調査に位置づけられていました。つまり、買収対象の工場や土地に土壌汚染、地下水汚染、廃棄物の不法投棄などの環境リスクが潜在していないかを確認し、それに基づいて価格交渉や契約条件を調整するための「リスク回避ツール」として運用されてきたのです。このように、従来の環境DDは「資産や事業を取得する側の立場から行われる防御的な調査」としての性格が強く、スコープ(調査範囲)も対象拠点の過去の土地利用や環境法令遵守状況、環境インフラの状態などに限定されがちでした。
しかし近年、この環境DDのスコープが急速に拡大しています。その背景には、環境問題をめぐるグローバルな社会的関心の高まり、ESG投資の拡大、そして法規制や情報開示要請の進化が挙げられます。特に注目されるのが、EUで進行中の「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」です。これは、企業が自社だけでなく、そのサプライチェーン上の取引先や下請企業に至るまで、人権・環境に関するリスクを特定し、是正措置を講じることを義務付ける法制度であり、環境DDがもはやM&Aの専用ツールではなく、国際ビジネスにおける基礎的な責任の一部と化していることを象徴しています。
CSDDDのような規制のもとでは、たとえばアパレル企業が自社ブランドを製造する委託先の染色工程における有害化学物質の排出状況を確認したり、電子機器メーカーがレアメタルの採掘サプライヤーにおける森林破壊のリスクを評価したりすることが求められます。このような調査は従来の「目の前の資産」に対する調査ではなく、「見えにくい連鎖の先」にある環境リスクに光を当てるものであり、企業の環境DDのスコープは「垂直」から「水平」へと広がっているといえるでしょう。
さらに、環境DDは「対外的な取引」のためだけに行われるものではなくなっています。近年では、企業が自らの環境リスクを能動的に評価し、持続可能性を高めるために行う「セルフデューデリジェンス(自社健全性調査)」のニーズが高まっています。これは特に、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)への対応や、GRI、ISSBなど国際的なサステナビリティ開示基準への適合を目指す企業において顕著です。
TNFDは、企業が自然資本に依存・影響しているリスクと機会を特定し、それを財務的観点から開示することを求めていますが、その前提として「どの事業がどの自然資源とつながっているのか」「自社のバリューチェーンにおいてどの地点にリスクが潜んでいるのか」といった精緻な自己理解が不可欠です。そのため、TNFD対応の第一歩として、セルフデューデリジェンスによって自社事業やサプライチェーンの構造を環境面から棚卸しする動きが広がっています。
このようなDDの自社適用は、単にリスクの洗い出しだけでなく、「価値創造の起点」としての意味も持ちます。たとえば、再生可能エネルギーの導入可能性、生物多様性保全による地域連携、資源循環の仕組み構築など、環境と経営を統合する施策を構想するうえで、環境DDは計画立案の土台となるのです。こうした活用は、サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブといった概念との親和性も高く、自治体やインフラ事業者による導入も進みつつあります。
また、サプライチェーン上の調査やセルフデューデリジェンスを進める際には、環境調査や計量証明の専門知見を持つ外部機関との連携が欠かせません。対象地の過去履歴の収集、水や土地、生物多様性への影響やグローバルNGOの動向情報など、多様化するリスクに対応した高度かつ適切な調査手法の駆使が求められ、企業の内部リソースだけで完結することは難しくなっています。
こうした文脈の変化をふまえ、環境DDという言葉が意味するものは今や「ある資産のリスク調査」から、「組織全体の環境リスクマネジメント」へと変貌しつつあるといえるでしょう。リスク管理、開示対応、価値創造、そして社会的責任――こうした複数の目的を同時に果たせるからこそ、環境DDはその応用範囲を着実に広げています。
まとめ
かつてM&Aの現場で限定的に使われていた「環境デューデリジェンス」という手法は、いまやグローバル企業のサプライチェーン管理や、TNFDをはじめとするサステナビリティ情報開示の基盤として、幅広い場面で活用されています。古典的なスコープが「取得資産の環境リスク把握」だったのに対し、現在では「事業全体の環境健全性評価」や「予防的マネジメント」へと進化しています。環境DDは、単なる調査を超えた「経営インフラ」としての機能を持ち始めており、今後の企業価値やレジリエンスの向上に不可欠な要素となることは間違いありません。