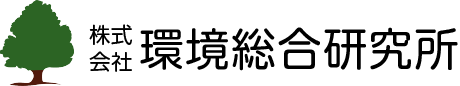不動産取得時に発覚した土壌汚染リスクへの対応事例
~地歴調査と土壌調査による環境リスク回避~
事例概要
本事例は、地方都市A市における製造業B社による不動産取得検討に際して実施された環境デューデリジェンス(以下、環境DD)に関するものです。B社は事業拡大を目的として、自社工場から車で5分圏内に位置する建物付き土地の購入を検討。価格の手頃さと立地の利便性から前向きな交渉に入りましたが、取引リスクの把握と将来の開発計画への支障を避けるため、当社に環境DDの実施を依頼されました。
調査内容と対応プロセス
当社が実施した環境DDでは、まず**地歴調査(フェーズ1)**により、当該地の過去の土地利用履歴を詳細に調査しました。その結果、過去の所有者は金属加工業を営んでおり、トリクロロエチレン(特定有害物質)の使用が確認されました。
この情報を踏まえ、**重点的な土壌調査(フェーズ2)**を実施。調査は過去の工場配置や排水動線を考慮した上で、汚染が想定されるエリアにスコープを絞り、ボーリング調査と土壌採取を実施しました。
調査から報告までのプロセスは以下のとおりです:
- 地歴調査(文献・資料調査、ヒアリング)
- 調査設計(リスクが高い地点の抽出)
- 土壌試料採取・分析(公定法準拠)
- 分析結果の評価・報告書作成
- リスク顕在化時の対応策検討
調査結果とリスク評価
土壌調査の結果、全体敷地面積のうち約20%において、トリクロロエチレンが土壌汚染対策法の基準値を超過する濃度で検出されました。これにより、仮にB社が当該地を取得・開発する場合、以下の重大な環境・事業リスクが判明しました:
- 開発行為の規制:A市により開発許可が下りない可能性
- 不動産価値の低下:潜在的な負債の計上リスク
- 汚染是正措置のコスト発生:数百万円~数千万円規模
- 企業ブランドやステークホルダーへの影響
当社は、これらのリスクについて定量的な影響評価と意思決定支援を行い、B社は総合的な判断により土地購入を中止する意思決定に至りました。
クライアントの声/導入効果
「当初は立地と価格の魅力で即断しそうになりましたが、環境DDを通じて重大なリスクが判明し、将来の損失を未然に防ぐことができました。地歴調査から土壌調査までスムーズかつ柔軟に対応いただき、判断材料として非常に有効でした。」
— B社 総務部ご担当者(仮名)
B社にとって、今回の対応は目に見えないリスクの顕在化と意思決定支援の成功事例となりました。
担当者コメント
今回の案件では、早い段階で環境リスクの検討をご依頼いただけたことが大きなポイントでした。地歴調査での業種判定、化学物質の使用履歴、施設の配置情報など、机上情報をもとに的確にリスク地点を特定し、調査コストも最適化できました。
当社では、調査の範囲や深度をクライアントの目的やスケジュールに応じて設計しており、事業計画の早期段階から関与することで、より
的確な意思決定支援が可能になります。
今後も、リスクを「見える化」し、事業の安全と持続性に貢献してまいります。
— 株式会社環境総合研究所 環境リスク評価チーム 担当者
新興住宅地に隣接する物流倉庫用地取得時の騒音リスク評価事例
~操業後の苦情トラブルを回避する予測型環境デューデリジェンス~
事例概要
本事例は、物流倉庫業を営むB社が、北関東にある県営の工業団地への進出を検討した際に、将来的な環境リスクの洗い出しと対応策立案のため、当社に**環境デューデリジェンス(環境DD)**をご依頼いただいたものです。
対象地は、工業専用地域として県が整備した工業団地内の一画で、土壌汚染対策法に基づく調査手続きは完了済み。地価や広さ、周辺インフラも含めて事業用地として高い魅力があり、B社は物流拠点としての取得と建設を前提に、最終的なリスク評価を希望されました。
調査内容と対応プロセス
今回の環境DDでは、土壌汚染やアスベスト等の物理的リスク調査に加え、操業後の周辺住民からの環境苦情リスク(騒音、振動など)に重点を置いた調査が求められました。
当社では以下の対応を実施しました:
- 都市計画図・用途地域情報の収集と将来計画の確認
- 近隣エリアの開発動向に関する自治体ヒアリング
- 倉庫設計図に基づいた想定騒音源の特定
- 24時間操業に伴う騒音予測シミュレーション
- 苦情リスクの評価と対策案の立案・提示
特に重要であったのは、対象地の隣接エリアが「第一種低層住居専用地域」に該当し、近い将来、新興住宅地として分譲・建築される計画が存在していた点です。現地訪問時点では住宅の建設は始まっておらず、現地観察のみでは見逃されがちな将来的な苦情リスクが潜んでいました。
調査結果とリスク評価
騒音シミュレーションの結果、物流倉庫から発生するトラックの出入り音、荷下ろし作業音、室外機音、アイドリング音などが、将来的に建築予定の住宅との距離を踏まえると、受忍限度を超える可能性が高いと評価されました。
この結果を受け、当社では以下のような設計・運用レベルでの是正対応策を提案しました:
- 騒音源設備の配置転換
- 積み下ろしエリアの変更
- 遮音性能の高い建屋外壁材の採用
- 住宅地側に緩衝緑地帯を設ける計画の導入
これらの提案はすべて、最終的な倉庫設計図に反映され、B社は環境苦情リスクを低減した形で施設建設を進めることができました。
クライアントの声/導入効果
「工業団地内だから問題ないだろうと判断していましたが、用途地域の境界と開発計画に目を向けることで、新たなリスクに気づけました。騒音という“見えないリスク”に対し、予測・評価・対策まで一貫して提案いただけたことで、安心してプロジェクトを進められました」
— B社 開発担当部長(仮名)
B社にとっては、設計段階での対応が可能だったことで、苦情対応のコストやブランド毀損を未然に回避できる結果となりました。
担当者コメント
本件では、「工業団地=苦情リスクがない」という先入観が、実は大きな落とし穴となりかねない状況でした。都市計画情報の読み解きと将来の住環境との接点把握により、“今は問題がなくても、数年後には大きな問題になる”可能性を可視化できたことが成果だと感じています。
環境デューデリジェンスというと土壌やアスベストなどの物理リスクが注目されがちですが、操業リスク(騒音、振動、臭気等)も商業系不動産では極めて重要な要素です。当社では、シミュレーションや将来予測を活用した実践的な評価も得意としています。
— 株式会社環境総合研究所 環境影響予測チーム 担当者
美術製作会社における労働安全衛生リスクの是正事例
~顧客からの信頼に応える「セルフ環境DD」による職場改善~
事例概要
本事例は、首都圏に拠点を置く展示物・造形物制作を手掛ける美術製作会社C社が、取引先からの要請を契機に、自社の環境リスクの健全性を確認するために当社へ**環境デューデリジェンス(環境DD、セルフDD)**を依頼された事例です。
C社は、大手イベント会社や広告代理店などとの多数の取引実績を有しており、ESG時代においてサプライチェーンの健全性が重要視される中、主要顧客からの取引先健全性調査への対応が必要となっていました。その一環として、「第三者による環境面の健全性評価(エビデンス)」が求められ、当社によるセルフ環境DDを導入されました。
調査内容と対応プロセス
当社が実施した環境DDでは、典型7大公害(大気、水質、土壌、地盤沈下、騒音、振動、悪臭)に関するリスクだけでなく、労働安全衛生や有害物質管理、作業環境整備状況なども含めた多面的な環境評価を行いました。
具体的な調査項目は以下の通りです:
- 法令遵守状況の確認(環境基本法、労働安全衛生法など)
- 作業環境(塗装工程、換気設備等)の確認
- 有害物質の使用・保管状況
- 労働災害リスクの評価
- 文書管理状況(作業手順書、安全衛生マニュアル等)
調査の過程で、C社の塗装ブースにおいて、法令で義務付けられている作業環境測定が実施されておらず、さらに局所排気装置の性能が有機溶剤中毒予防規則の基準を満たしていないことが確認されました。
調査結果とリスク評価
今回の環境DDにおいて、以下の重大な労働安全衛生リスクが明らかになりました:
- 【法令未遵守】労働安全衛生法第65条等に基づく作業環境測定の未実施
- 【技術基準未達】局所排気装置の風速不足・排気能力不備
- 【作業手順の不徹底】保護具(マスク)の使用基準とフィット性確認の未実施
このまま運用を継続していた場合、以下のリスクが顕在化する恐れがありました:
- 労働基準監督署からの行政指導や刑事処分
- 顧客からの信頼失墜・取引停止
- 作業者の労働災害(有機溶剤中毒など)
当社では、これらの法令・労務リスクを総合的に評価した上で、是正優先順位と実行策を提示しました。
クライアントの声/導入効果
「当初は環境DDといえば“土壌汚染”や“大気汚染”のようなリスクを想定していましたが、まさか自社の労働安全衛生体制にここまで改善点があるとは思いませんでした。
第三者評価という形で指摘を受けたことで、社内でも納得感を持って改善に取り組め、結果的に顧客への説明責任も果たすことができました」
— C社 総務・品質管理担当者(仮名)
C社では、調査結果を受けて直ちに対応を開始。以下のような改善策が講じられました:
- 局所排気装置の改修と基準適合確認
- 年1回の作業環境測定の定期実施
- 保護具(マスク)の着用義務化とフィットテストの導入
- 作業手順書の再周知と作業指導体制の強化
これにより、ESG経営や人権リスク対応に資する社内体制が整備されただけでなく、対外的な評価にもつながる取り組みとなりました。
担当者コメント
本件は、いわゆる“7大公害”ではなく、働く人の安全と健康を守る労働環境リスクの洗い出しが主眼でした。ESG時代において、労働安全衛生は環境(E)と社会(S)の両面にまたがる重要なリスク領域です。
今回のように、顧客からの要請に対し、科学的かつ第三者的な視点でエビデンスを提供することは、サプライチェーン全体の健全性を支える意味でも極めて有意義です。当社では、法令遵守の可視化、職場改善支援、レピュテーションリスク低減まで含めた多面的な環境DDをご提供しております。
— 株式会社環境総合研究所 労働環境・有害物質対策チーム 担当者
生物多様性リスクが招いた太陽光発電開発中止事例
~湿地開発と地域社会との摩擦から学ぶ、先手の環境デューデリジェンス~
事例概要
本事例は、再生可能エネルギー事業者であるD社が、北関東地域にて湿地を含む土地を対象としたメガソーラー発電所の開発計画を進める中で、地域の生態系保全と社会的受容性の壁に直面し、事業中止に至ったケースです。
D社は、カーボンニュートラル実現に貢献すべく、太陽光発電による大規模な再エネ事業を各地で推進していました。本案件でも、立地条件や日照条件、送電網への接続可能性などから高い開発適性が見込まれており、県への開発許可申請も提出済みでした。
しかし、計画地が生態系的に重要な湿地エリアであることに対して、地元住民および自治会から強い反発があり、行政を巻き込む深刻な対立に発展しました。
調査内容と対応プロセス
当社への直接的な依頼はありませんでしたが、事例分析の観点から、以下のような生物多様性に関連する環境リスク評価が欠如していたと考えられます:
- 生態系保全上重要な地域かどうかの事前評価(自然環境調査、文献調査)
- 既存の生物多様性関連条例・行政方針の確認
- 湿地の生態系サービス(雨水調整、水質浄化など)の把握
- 野生動物との衝突や生息環境の破壊による間接影響の想定
- 地域住民・ステークホルダーとの合意形成プロセスの設計
F社は事業者として環境影響評価制度上の基準を満たすことに留まり、地域との協調や生態系リスクの戦略的評価を軽視していた可能性があります。
調査結果とリスク評価
開発予定地には、以下のような生物多様性リスクが存在していました:
- 【物理的影響】湿地の埋立てによる生息地の喪失
- 【間接影響】太陽光パネルや送電設備による野生動物の行動変容・衝突リスク
- 【生態系サービスの損失】雨水貯留機能、水質浄化、炭素固定能力などの喪失
- 【地域の環境レジリエンス低下】気候変動時代における地域防災力の低下
これらの影響を憂慮した地元自治会は、県および市に対して開発不許可を求める嘆願活動を展開。結果として、県は開発許可を見送り、さらに市では対象湿地の保全を目的とした新条例が制定されました。
この対応により、D社は当該エリアでの将来的な開発が事実上不可能となり、重大な機会損失と社会的信用の低下を被る結果となりました。
クライアントの声/導入効果(仮想)
「再エネ推進は環境に良いことだという思い込みがありましたが、同時に地域の自然や生活との共生が問われていたことに気づくのが遅すぎました。
今後は、事業性評価と同時に、環境・社会面からの事業妥当性の検証も欠かせないと痛感しています」
— F社 開発部マネージャー(仮名)
担当者コメント
本事例は、「再エネ=環境に良いこと」とする単純な構図が、時に別の環境問題や社会的摩擦を引き起こし得ることを象徴しています。
生物多様性リスクは、もはやCSRや自然保護の問題ではなく、企業の事業継続性・地域社会からの受容・規制対応力・レピュテーション評価に直結する経営課題です。
当社の環境デューデリジェンスでは、土壌や大気といった典型リスクだけでなく、自然資本・生態系サービスの視点から、事業と自然の共生可能性を科学的に評価します。
持続可能な地域づくりと企業成長の両立に向けて、ぜひ早期段階からの活用をご検討ください。
— 株式会社環境総合研究所 生物多様性リスク評価チーム 担当者
M&A後に発覚した排水施設の環境債務事例
~見えにくい老朽リスクが引き起こした数千万円の想定外コスト~
事例概要
本事例は、製造業A社が同業のB社をM&Aにより買収・経営統合した際に、クロージング後に老朽化した排水処理施設に起因する環境債務が発覚し、当初の経営統合計画に大きな影響を及ぼしたケースです。
B社は地方都市に本拠を構え、技術力の高い製造業者として評価されていました。幹線道路に近接した工業専用地域に立地する基幹工場も、事業シナジーや拠点統合の観点から極めて有望な資産として、A社によるM&Aの対象となりました。
買収にあたっては、財務・法務のデューデリジェンス(DD)に加え、環境面についても法令遵守状況や過去の測定データ確認等の文書ベースの調査が実施され、特段のリスクは確認されませんでした。
調査内容と対応プロセス
M&A成立後、A社は統合プロセス(PMI)の一環として、改めて自社グループの環境リスク評価を実施。当該プロセスでは、環境方針の統一や管理体制の再整備、現場点検、環境監査などの施策が段階的に進められました。
その過程で明らかになったのが、B社工場の排水処理施設の重大な劣化と処理性能の低下です。とりわけ有害物質(重金属等)の除去能力が著しく低下しており、排水中の濃度が排水基準を恒常的に超過していたことが判明しました。
実はB社では、定期測定前に場当たり的な応急修繕を実施して一時的に基準をクリアすることで、長年根本的な改修を先延ばしにしていたことが、内部監査で明らかになったのです。
調査結果とリスク評価
クロージング後に発覚した環境リスクは、A社にとって**「簿外の環境債務」**とも言えるものであり、以下のような事業影響が生じました:
- 【設備改修コスト】老朽排水処理施設の全面改修に数千万円規模の投資
- 【事業スケジュールの遅延】改修期間中の操業停止と出荷遅延
- 【経営計画への影響】統合スケジュールの見直し、中期計画の再策定
- 【レピュテーションリスク】排水基準超過に伴う行政指導・近隣地域からの不信
A社としては、買収前の環境DDでリスクの把握が不十分であったことを反省点とし、今後のM&Aでは初期段階からの環境リスク評価の重要性を再認識する結果となりました。
クライアントの声/導入効果(仮想)
「財務・法務DDで大きな懸念は見られなかったため安心して進めましたが、現場レベルでのリスクまでは把握できていませんでした。
クロージング後にここまで影響が出るとは想定外でした。今後は環境DDのスコープ設計を見直し、**“現地を見る”ことの重要性を社内で共有していきたいと思います。」
— A社 経営企画室 担当者(仮名)
担当者コメント
本事例は、排水処理施設という設備リスクが「見えにくい簿外債務」としてM&A後に顕在化した典型例です。文書確認やヒアリングといった間接的調査では、現場の運用実態までは把握しきれないケースが多く、特に設備の老朽化や場当たり的運用の継続は、将来的に大きな環境コストを招く要因となります。
当社の環境デューデリジェンスでは、こうした背景を踏まえ、現地調査、排水負荷と処理能力の比較、老朽度評価などを組み合わせて、「将来発生し得るリスク」までを可視化する調査設計を行っています。
製造業におけるM&AやPMIを円滑に進める上で、環境リスクの早期発見は極めて重要です。事業価値を守るための「守りのDD」として、ぜひご活用ください。
— 株式会社環境総合研究所 施設・排水リスク評価チーム 担当者
廃棄物処理施設跡地の不動産取引における環境リスク評価事例
~土壌汚染・コンプライアンス・インフラを網羅する多面的デューデリジェンス~
事例概要
本事例は、ある企業が千葉県N市の工業団地内に位置する約3,970坪の不動産(土地・建屋)について取得を検討するにあたり、当社に環境デューデリジェンス(環境DD)をご依頼いただいたものです。
対象地は、かつて産業廃棄物処理業を行っていた事業者(以下、旧事業者)が使用していたもので、現在は千葉県と産業廃棄物処理業許可取消処分を巡る係争中となっていました。
クライアントは本物件の取得に先立ち、土壌汚染リスクを中心に、コンプライアンス、インフラ、周辺環境など多面的な観点から環境リスクを評価し、取引の可否判断および将来的な是正対応の検討に役立てたいという目的で当社へ調査を依頼されました。
調査内容と対応プロセス
当社は、本環境DDにおいて以下の主要な観点から調査を実施しました:
【1】土壌汚染リスク調査
- 地歴調査による過去の土地利用状況の確認
- 周辺地域で過去に実施された土壌調査データの収集・分析
- 旧事業者関係者へのヒアリングにより、特定有害物質の使用実態や廃棄物処理履歴を把握
- 千葉県ヤード・残土課と協議のうえ、フェーズ2としての法令に基づく土壌調査計画の準備(オプション対応)
【2】その他環境・コンプライアンスリスク調査
- 大気・騒音・振動・悪臭・水質等、典型6公害の関連法令への適合状況の整理
- 建物内アスベストの使用有無、建築確認状況
- 上下水道を含むインフラの現況確認
- 交通アクセス、搬入経路、近隣住居・学校・病院の有無といった周辺環境に関するビジネスリスクの洗い出し
- 過去の環境訴訟・行政処分の有無に関する調査(旧事業者が県と係争中の訴訟の把握も含む)
調査結果とリスク評価
調査の結果、以下のようなリスクが潜在的に存在する可能性が示唆されました:
- 【土壌汚染リスク】旧事業者の事業内容と土地利用履歴から、特定有害物質による土壌汚染の端緒情報を複数確認
- 【コンプライアンスリスク】旧事業者が行政処分(産廃処理業許可取消)を受けた事実と、係争中であることにより、取得後の風評リスクやレピュテーションリスクが懸念される
- 【ビジネスリスク】一部インフラ整備に不確実性があり、将来的な活用用途に制約が生じる可能性あり
なお、土壌調査フェーズ2を実施することで、より確定的なリスク把握が可能となるため、本件についてはリスク管理上、次フェーズでの詳細調査が推奨される結果となりました。
クライアントの声/導入効果(仮想)
「書類確認だけでは見えにくい過去の利用実態や、周辺地域の法令適合状況、許可取消の背景など、想定以上に重要なリスク情報が得られました。
取引判断の材料としても、社内への説明責任の観点からも、第三者評価を得たことは非常に有意義でした」
— 不動産開発会社 担当者(仮名)
担当者コメント
本件では、行政処分歴のある旧産廃施設跡地という社会的・環境的な複合リスクを内包する不動産を対象に、書面・現地・ヒアリング・公開情報の全方向からリスク分析を行いました。
土壌汚染やインフラ不整備といった物理的リスクのみならず、レピュテーションや訴訟の影響など、事業性や社会的信頼性にも関わる要素を包括的に把握することが重要です。
当社の環境デューデリジェンスでは、取得の成否判断だけでなく、リスク顕在化後の是正費用・対策方針の検討にも貢献できるよう、調査スコープを柔軟に設計しています。
複雑な背景を持つ不動産取得の際は、ぜひ早期段階からご相談ください。
— 株式会社環境総合研究所 不動産・施設リスク調査チーム 担当者